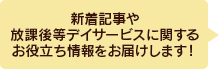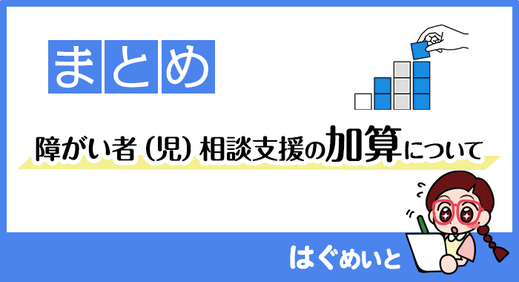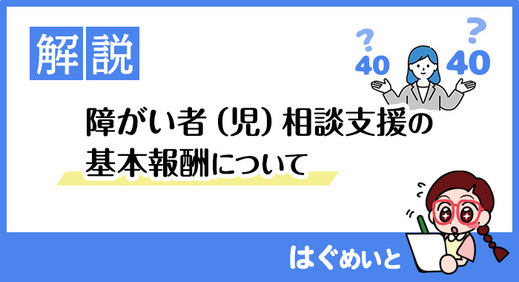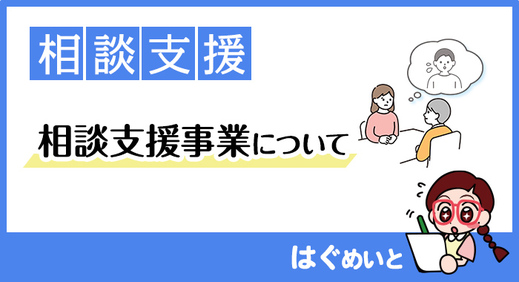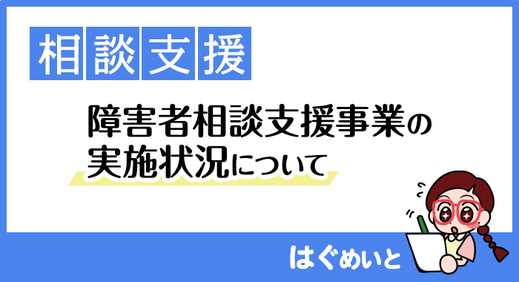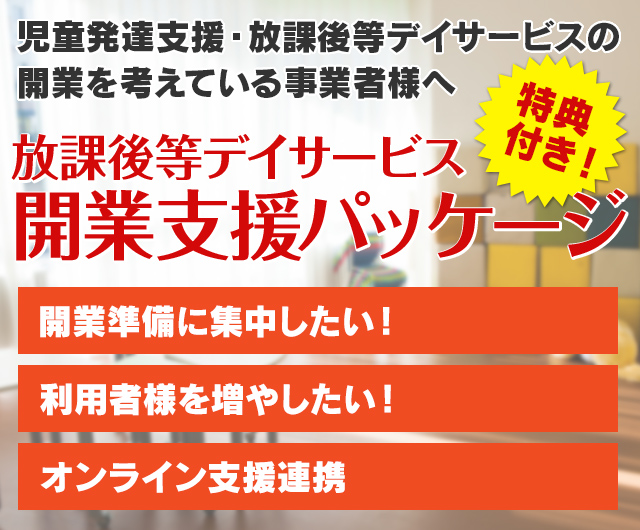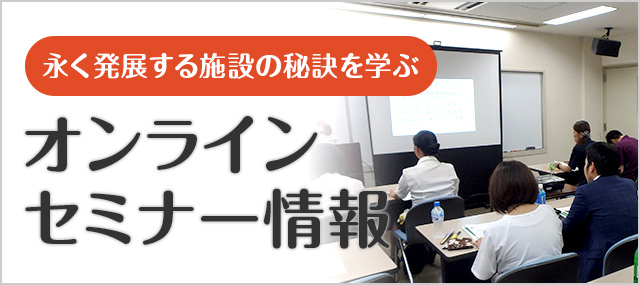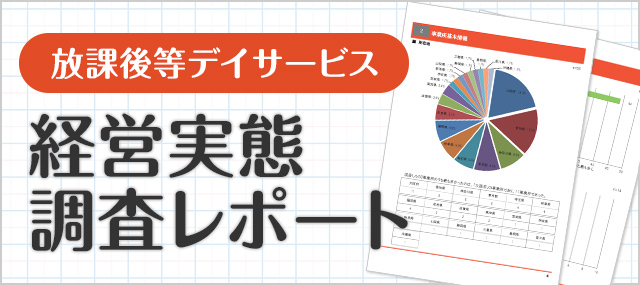放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
相談支援に関するQ&A Vol.1
2025/07/08
相談支援 お役立ちコラム
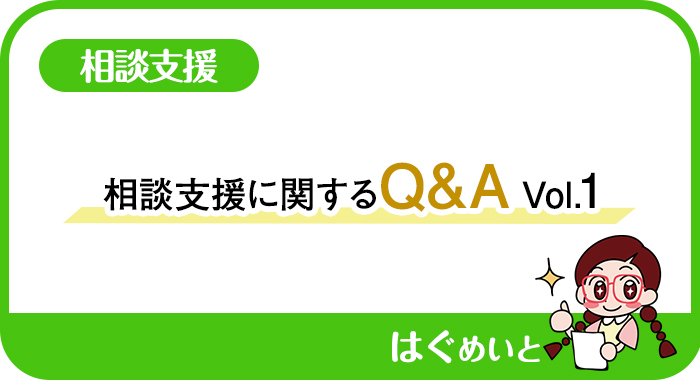
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は相談支援に関するQ&Aをまとめました。
相談支援に関わる皆さまに向けては、これまでに以下の記事をご紹介しています。
▶ 相談支援事業所について
▶ 障害者相談支援事業の実施状況について
▶ 【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について
▶ 【まとめ】障がい者(児)相談支援の加算について
この記事では、相談支援事業について、Q&A形式でお伝えします。
参考資料:
厚生労働省:相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)
厚生労働省:相談支援に関するQ&A(令和7年3月18日)
相談支援事業とは
相談支援とは、障がいのある方やそのご家族が自立した生活を送るために、日常生活や社会生活上の課題に対応するための支援を提供する制度です。
適切な福祉サービスの利用を促進し、利用者の生活の質を向上させることを目的として、相談支援は、サービス等利用計画の作成や、地域の関係機関との連携を通じて実施されます。
相談支援事業の目的は、障がいのある方が自分らしい生活を送るために、必要な支援を提供することです。
そのため、市町村、相談支援事業所、医療機関、福祉サービス事業者など多くの機関が連携しながら行われる事業になり、市町村などより委託された相談支援事業所においても「相談支援」が行われます。
相談支援事業所を運営する上での詳細は、以下よりQ&A形式で説明します。
1. 指定基準関係
【設備基準】
指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。
○ 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
H25.2.22 相談支援関係Q&A 問1より
【受給資格の確認】
指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。
○ 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。
なお、サービス等利用計画案等の作成時点においては、市町村が通知する計画作成依頼書により市町村から依頼を受けた対象者であることを確認する。
H25.2.22 相談支援関係Q&A 問2より
【取扱件数】
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。
○ 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対応できる件数や人数とすること。
H25.2.22 相談支援関係Q&A 問3より
【補助の業務】
サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員及び相談支援員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有しておらず、相談支援員でもない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか。
○ サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、以下のとおりである。
・ 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメント及びモニタリングの実施
・ サービス等利用計画(案)の作成
・ 利用者等へのサービス等利用計画(案)等の説明
・ サービス担当者会議における利用者等及びサービス担当者への質問・意見の聴取
○ なお、相談支援員については、以下の業務を行うことを可能としている。(指定基準第15条 第2項 第1号から第9号及び第3項(第3条第5号による読み替え)参照)
・ サービス等利用計画の原案の作成(利用者へのアセスメントを含む)
・ モニタリング
この場合、サービス等利用計画の作成者は相談支援専門員となり、モニタリングの担当者は相談支援員となる。
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問4より
【アセスメント等】
計画相談支援及び障害児相談支援の指定基準において、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する際の留意点として「相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、必ず利用者(障害児)の居宅を訪問し、利用者(障害児)及びその家族に面接して行わなければならない。」と規定されているが、次の場合についてはどうか。また、モニタリングについてもどうか。
(1) 自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所、日中通っている障害福祉サービス事業所等、保育園等で行ってもかまわないか。
(2) 作成時は、上記(1)の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。
○ サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、障害者及び障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児及びその家族からの聞き取りだけでなく、障害者及び障害児が居所において日頃生活している様子や生活環境等を実地で確認する必要があるため、障害福祉サービス事業所等の一時的な滞在場所のみを訪問して面接を行う場合には適切にアセスメント又はモニタリングが行われたものとは認められず、自宅訪問が必要である。そのため、(1)及び(2)ともに認められない。
○ なお、居宅の訪問による面接に加えて、障害福祉サービス事業所等における面接を行った上でアセスメント又はモニタリングを行うことは問題ないため申し添える。
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問5より
アセスメント又はモニタリングに係る訪問については、必ず利用者の居宅、障害者支援施設等、精神科病院(障害児の場合は居宅)を訪問しなければならないこととされているが、利用者の通所先の障害福祉サービス事業所等を訪問して面接を行う場合、アセスメント又はモニタリングとして認められるか。
○ 利用者が居所において日頃生活している様子や生活環境等を実地で確認する必要があるため、障害福祉サービス事業所等の一時的な滞在場所のみを訪問して面接を行う場合、適切にアセスメント又はモニタリングが行われたものとは認められない。なお、居宅の訪問による面接に加えて、障害福祉サービス事業所等における面接を行った上でアセスメント又はモニタリングを行うことは問題ないため申し添える。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問6より
サービス担当者会議の実施について、参加者の予定の調整が付かない場合、サービス担当者会議の参加を求めず、別に個別に意見調整を行うことで対応してもよいか。
○ 極力一同に各福祉サービスの担当者を集めてサービス担当者会議を行うことが望ましいが、全担当者の参加が困難な場合については、主要な担当者の参加を求めた上でサービス担当者会議を開催することとし、その他の担当者については、事前に個別に意見調整を行い、当該意見は会議当日に参加者に共有することとして差し支えない。なお、その場合、参加できなかった担当者に対しては、会議での議論内容を共有の上、必要に応じて改めて意見聴取すること。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問7より
指定基準第15条第3項第3号の関係で、解釈通知に規定されているサービス等利用計画の「軽微な変更」とは、具体的にどのような内容が含まれるか。
○ 軽微な変更については、支給決定を要しない範囲の計画変更内容と解すべきであり、当該軽微な変更については、サービス等利用計画作成の一連の業務は不要である。なお、支給決定を伴わないサービス等利用計画の変更については、サービス利用支援費の支給対象外となるため、その点についても留意されたい。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問8より
2. 指定事務関係
【相談支援専門員】
相談支援専門員の要件となる実務経験について、以下のいずれの考え方が正しいか。
(1) 180日以上勤務した年が○年ある必要があり、180日従事していない年は実務経験に含めることができない。
(2) 勤務期間が通算で○年以上かつ勤務日数が○年×180日以上を満たしていればよく、180日従事していない年があってもよい。
(2)の考え方が正しい。
○ 主任相談支援専門員研修の受講要件、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験、基礎研修、実践研修の受講要件についても同様の考え方である。
○ なお、相談支援従事者現任研修、サービス管理責任者更新研修の受講については、必ずしも1年につき180日以上の実務経験を求めるものではない。
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問13より
相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の実務経験要件にある、「相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められるもの」の基礎的な研修とは何を指すのか。
○ 介護職員初任者研修(旧ヘルパー研修2級)に相当するものが該当する。
○ なお、介護職員初任者研修以上の内容を取り扱う研修についても含まれるものであり、例えば、介護職員実務者研修が該当する。
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問14より
相談支援専門員の実務経験要件について、国家資格等に基づく業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以上となっているが、国家資格等に基づく業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合は、どちらにも算定してよいか。
○ お見込みのとおり。例えば、国家資格等に基づく業務が相談支援業務にも該当する場合は、8年以上の実務経験が必要なものではなく、5年以上の実務経験で足りることとなる。
○ なお、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者についても同様である。(サービス管理責任者の場合は、国家資格等に基づく業務の期間は3年以上となる。)
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問15より
保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。
○ お見込みのとおり。
なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。
H25.2.22 相談支援関係Q&A 問16より
相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者である配置要件である実務経験について、一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業等が対象となっているが、これに準ずるものとしてはどのようなものが考えられるか。
○ 障害者相談支援事業、基幹相談支援センター等における業務をはじめとする地域生活支援事業における相談支援業務のほか、例えば、生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、地域居住支援事業)等の相談支援業務が含まれるものと考えている。
○ なお、平成24年の改正法施行前の「相談支援事業」についても実務経験に含まれるため、申し添える。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問20より
相談支援専門員の実務経験要件について、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に従事していた期間は対象となるが、地域包括センターにおける相談支援の業務(介護予防支援事業を除く。)に従事した期間は対象となるか。
○ 居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に準ずるものとして認めて差し支えない。
R3.4.8 相談支援関係Q&A 問17より
【兼務】
指定基準及び報酬算定上、相談支援専門員及び相談支援員については、「基幹相談支援センターまたは障害者相談支援事業等」の業務と兼務することを認めるものとしているが、「等」とは具体的にどのような内容が含まれるか。
○ 地域生活支援事業における相談支援に関する事業を想定している。具体的には以下のとおり。なお、いずれも当該業務を委託する自治体が認める場合に限ることに留意されたい。
・都道府県相談支援体制整備事業
・地域生活支援拠点等における拠点コーディネーターの業務
・医療的ケア児支援センター
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
・発達障害者支援センター
・障害者就業・生活支援センター
・障害児等療育支援事業
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問22より
相談支援専門員、相談支援員について、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)との兼務は可能か。
○ 計画相談支援、障害児相談支援に係る指定基準上の取扱いとしては、介護支援専門員との兼務は可能である。
また、計画相談支援、障害児相談支援の機能強化型基本報酬の算定にあたっても、相談支援専門員が居宅介護支援事業の主任介護支援専門員(介護予防支援事業の介護支援専門員)と兼務する場合に限り、原則として可能とする。
もっとも、機能強化型基本報酬の趣旨である、支援の質の高い相談支援の実施の観点を踏まえ、専ら障害者への相談支援に従事する者が配置されていない等、障害者への十分な支援が期待できないと考えられる場合は算定を認めないこととされたい。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問23より
管理者について、指定特定(障害児)相談支援事業所に併設され、一体的に管理運営する事業所における管理者の業務との兼務は可能とされているが、併設される事業所以外の事業所における管理者の業務との兼務は可能か
○ 基本的には併設される事業所以外の事業所における管理者の業務は兼務すべきでないが、管理業務に支障がないと市町村が認める場合は差し支えない。
R6.4.5 相談支援関係Q&A 問24より
3. 支給決定通知・事務処理要領、4. 報酬関係は、こちら▶▶
まとめ
相談支援事業および相談支援専門員の業務は、障害者総合支援法により明確に定義されています。
厚生労働省の『相談支援事業の手引き』に引き続き、Q&Aが発表されました。
例えば、「相談支援事業所に障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所が併設されている場合は、運営に支障がない場合に限り相談室を兼用して差し支えない。」など設備基準も含めて詳しく掲載されています。
相談支援の運営に疑問がございましたら、こちらのQ&Aをご参照ください。
さいごに
弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。
また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。
相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
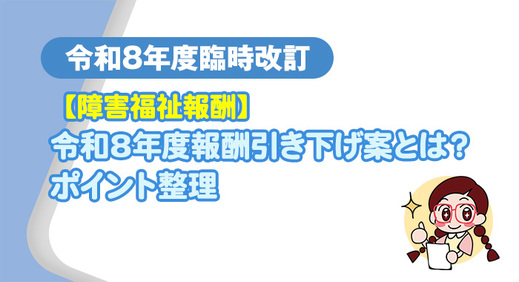
【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理
-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】
-
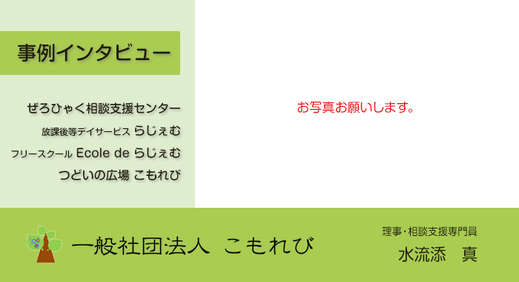
相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】
-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!
-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】
-
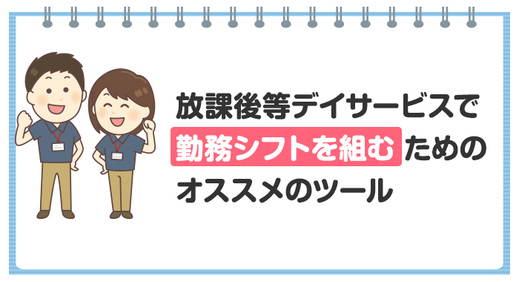
【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順
-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】
-
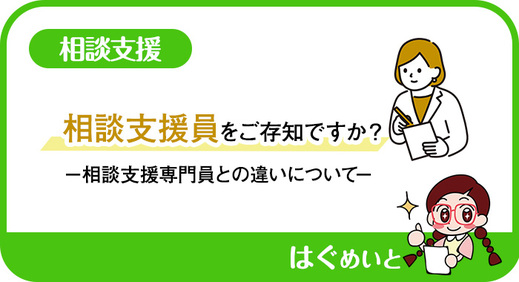
相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-
-
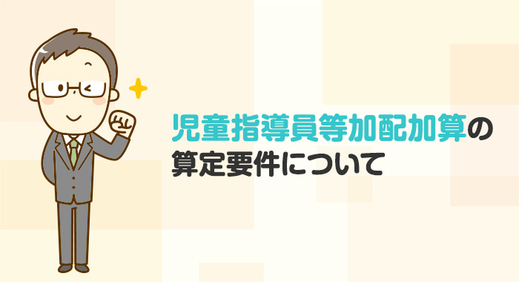
児童指導員等加配加算の算定要件について
-

「自然保育」の理念のもと保育と療育で子どもを支援【株式会社モアスマイルプロジェクト様】
-