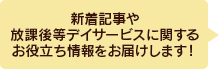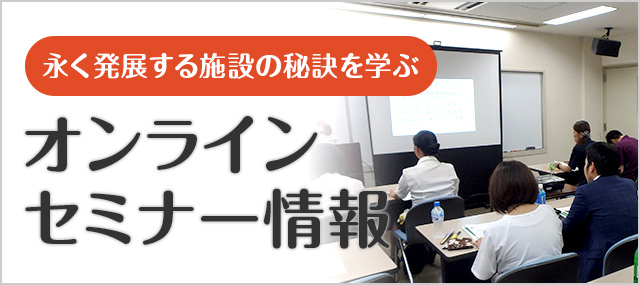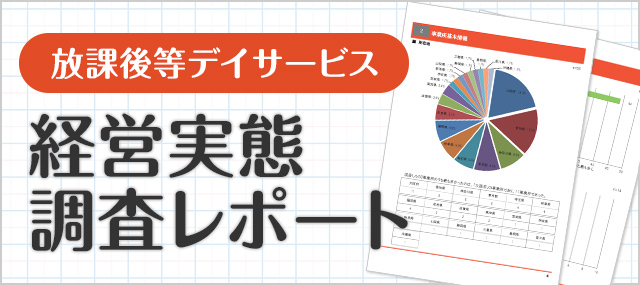放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
【加算活用事例】子育てサポート加算と家族支援加算~令和6年報酬改定~
2025/06/10
放課後等デイサービス 報酬改定2024
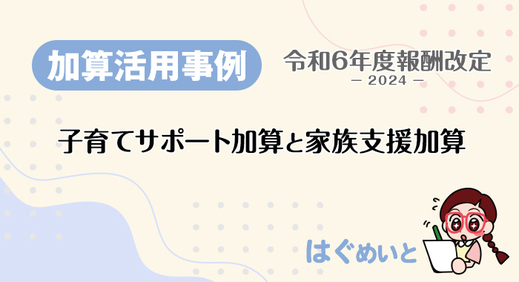
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報の中から子育てサポート加算と家族支援加算について、具体的な活用事例をお伝えします。
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」令和6年4月1日
・「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A 一覧」令和6年6月10日時点
・「放課後等デイサービス ガイドライン」令和6年7月
・「児童発達支援 ガイドライン」令和6年7月
【令和6年報酬改定】子育てサポート加算のまとめ
2024/08/01
放課後等デイサービス 報酬改定2024
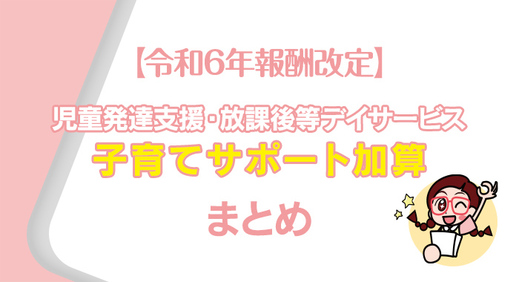
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
子育てサポート加算について、お伝えします。
【令和6年報酬改定】新設・見直しにより計画の作成等が必要な加算一覧
2024/06/19
放課後等デイサービス 報酬改定2024
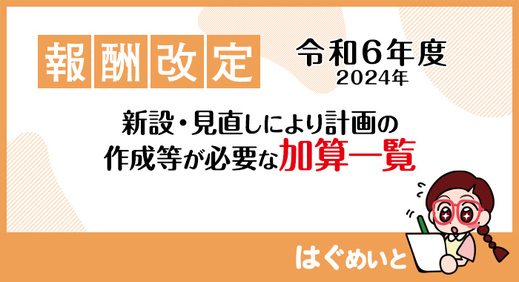
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するまとめ情報です。
障がい児通所支援・訪問支援の報酬改定における加算の新設・見直しにより、令和6年4月1日以降に計画書や個別支援計画への記載等が必要になった加算の主な要件と留意事項をまとめました。
ココトモワークス「子育て支援講演会」のご案内
2023/07/19
障害福祉施設向け最新ニュース

みなさんこんにちは!
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援向け施設運営システム「HUG」を提供する株式会社ネットアーツが、2023年9月に開所を予定している「就労移行支援・就労継続支援B型事業所 ココトモワークス犬山」「放課後等デイサービス ココトモワークスジュニア犬山今井校」。
開所を前に、元小学校教師・子育てアドバイザーの羽田野 富喜子先生による子育て支援講演会を開催しますので、ご紹介させていただきます。
続きを読む知的障害や発達障害のある子どもたちの「運動会が楽しみになる親の考え方」
2023/05/08
小児発達専門看護師 佐々木先生コラム
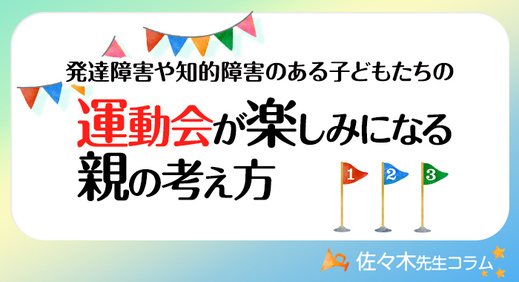
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は保護者様や児童と関わる皆様にお役立ていただける内容をご紹介します。
続きを読む発達障害や知的障害のある子どもたちの「季節の変わり目の体調不良対策」とは
2022/09/15
小児発達専門看護師 佐々木先生コラム
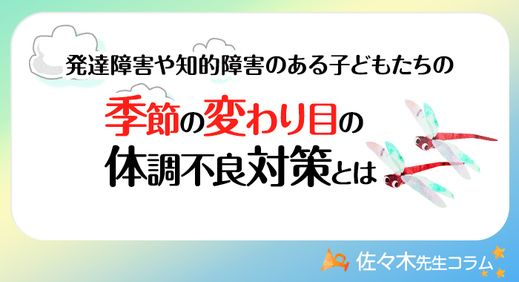
こんにちは。小児発達専門看護師で知的障害児の母でもある佐々木美華です。
夏休みも終わり、2学期が始まりましたね。
お子様たちはいかがお過ごしでしょうか?
ここ最近、朝晩の温度差を感じるようになってきました。
温度差が大きくなる季節の変わり目は、大人でも体調不良になりやすいですよね。
発達障害や知的障害のお子さんがいる親御さんたちは、この時期のお子さんの様子で
「朝から身体がだるそうでボーっとしている」
「あまりご飯をたべてくれない」
「イライラしてかんしゃくが増えた」
など、お悩みをではないでしょうか?
発達障害や知的障害のある子どもたちの熱中症を防ぐ3つの対策とトレーニング方法とは
2022/07/19
小児発達専門看護師 佐々木先生コラム
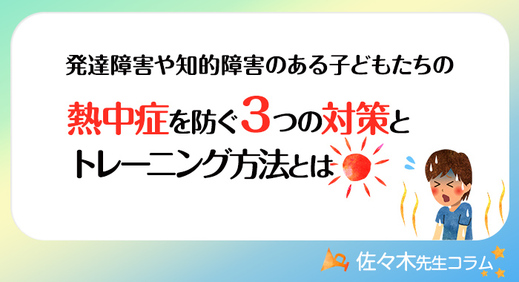
こんにちは。小児発達専門看護師で知的障害児の母でもある佐々木美華です。
今回から、はぐめいとのコラムを書かせていただくことになりました。
20年間の看護師・保健師としての仕事と障害児子育ての経験から「知的障害、発達障害のある子と親が穏やかに過ごすために出来ること」についてお伝えしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、猛暑が続くこの季節、熱中症が心配ですね。
特に発達障害や知的障害のある子どもは、熱中症になりやすいために注意が必要です。
発達障害や知的障害のある子どもが熱中症になりやすい原因は、主に3つあります。
その具体的な理由をお伝えします。
【後編】まずは事業所としての基盤を固め、いずれは重心に特化した施設を作りたい【株式会社NCK様】
2021/08/27
放課後等デイサービス事例インタビュー

熊本県熊本市東区にて、医療ケアがあっても通える児童発達支援・放課後等デイサービス『子育て支援センターサンライズ』を運営する株式会社NCK様にお話を伺うことができました。
重症心身障害児を対象とした施設を選んだ経緯や、保護者様同士が支え合う場を提供するためのコミュニティづくり、共に働く職員への思いや今後の展望などについて詳しくお話していただきました。
>>【前編】少数精鋭で多機能型を運営するには、能率を上げるシステムが不可欠でした【株式会社NCK様】
続きを読む【前編】少数精鋭で多機能型を運営するには、能率を上げるシステムが不可欠でした【株式会社NCK様】
2021/08/20
放課後等デイサービス事例インタビュー

熊本県熊本市東区にて、医療ケアがあっても通える児童発達支援・放課後等デイサービス『子育て支援センターサンライズ』を運営する株式会社NCK様にお話を伺うことができました。
重症心身障害児を対象とした施設を選んだ経緯や、保護者様同士が支え合う場を提供するためのコミュニティづくり、共に働く職員への思いや今後の展望などについて詳しくお話していただきました。
続きを読む保護者の気持ちに寄り添う4つの会話のポイント
2021/05/04
羽田野ふきこ先生の子育てコラム
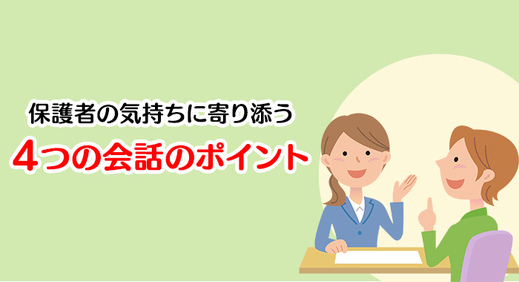
こんにちは。
元小学校教師で子育てアドバイザーの羽田野ふきこです。
野山には色とりどりの花が咲き乱れ、新緑の美しさが目に染みる季節になりました。
胸膨らませて進級・進学した子どもたちも、新しい教室や先生、クラスの友達や学校生活に慣れてきた頃でしょうか。
新しい環境に慣れるまでの一か月間は、緊張感の連続だったことと思います。
みんなよくがんばりました。
がんばった自分をほめてあげてほしいと思います。
子どもたちは、大人が思っている以上にがんばっています。
保護者の方やスタッフの方も、がんばった子どもたちを労ってあげてください。
子どもたちの張り詰めた糸は、このゴールデンウイークで一気に切れます。
そして、連休明けに体調不良や不登校になって現れるケースがみられます。
子どものサインの出し方は様々ですが、私が経験した中でよく見られたのは、
「腹痛や頭痛」
「足が痛い」
「病院で薬を処方してもらうが、症状が治らない」
「朝が起きられなくなる」
「食欲がない」
「だるい」
「学校の準備をすると涙が出る」
「怒りっぽくなる」
「みんなと登校をしたがらなくなる」
「なんとなく元気がない」
「表情が暗い」
などといったケースがありました。
こんなとき、お子さんを無理に学校へ連れて来られる保護者の方もいました。
なぜなら、子どもは学校に来てしまえば、普段通りまたがんばるからです。
しかしここで考えていただきたいことは、これが子どもの怠け心ではなく「SOS」であるということです。
4月の緊張感からくる疲れかもしれかもしれません。
身近な人との関係からくるストレスかもしれません。
ただ、一つ言えることは、子どもたち自身にも分からないということです。
サインが出たときは、「無理をしない・させない」「子どものサインに蓋をしない」ことです。
そして、そのサインを見過ごさないためにも、保護者や先生、放課後等デイサービスのスタッフの方々で、引き続き子どもたちの体調管理に気を配っていただきたいと思います。
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
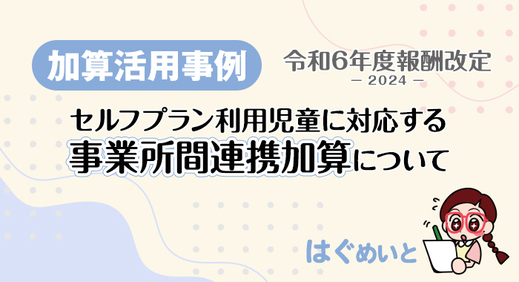
【加算活用事例】セルフプラン利用児童に対応する事業所間連携加算についてー令和6年報酬改定ー
-
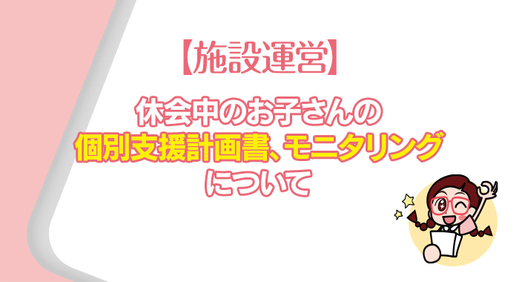
【施設運営】休会中のお子さんの個別支援計画書、モニタリングについて
-
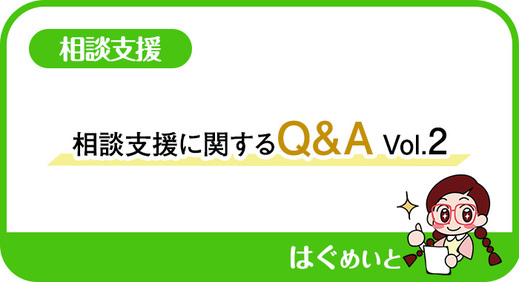
相談支援に関するQ&A Vol.2
-
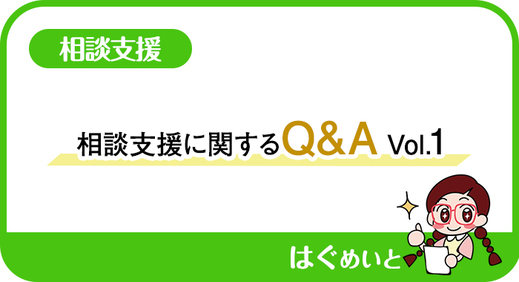
相談支援に関するQ&A Vol.1
-

~誰ひとり取り残さない居場所を創る~農福連携×福祉事業見学ツアーを開催!
-
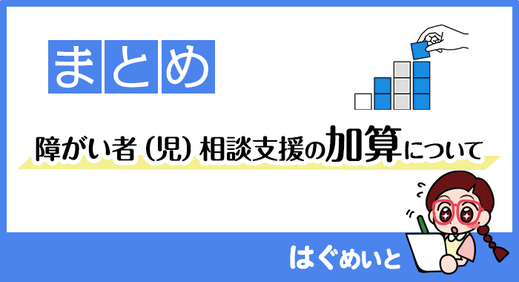
【まとめ】障がい者(児)相談支援の加算について
-
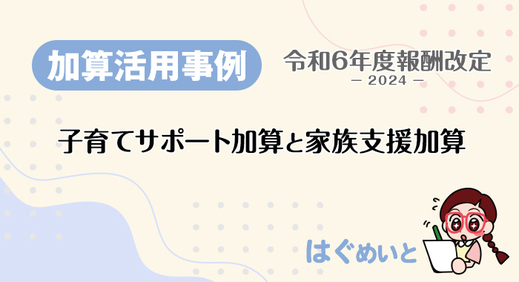
【加算活用事例】子育てサポート加算と家族支援加算~令和6年報酬改定~
-
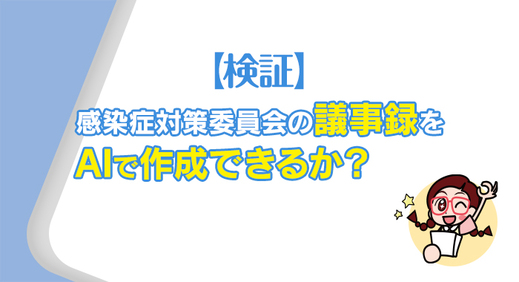
【検証】感染症対策委員会の議事録をAIで作成できるか?
-

家族のために、そして子どもたちの将来を考えて【合同会社TULA様】
-
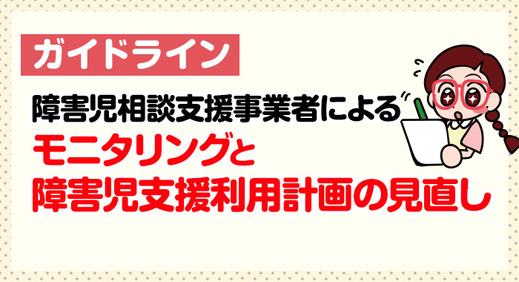
【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて
-