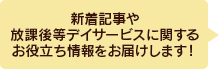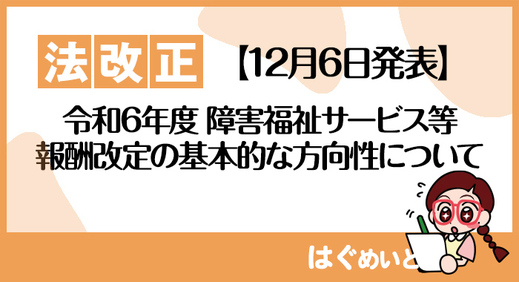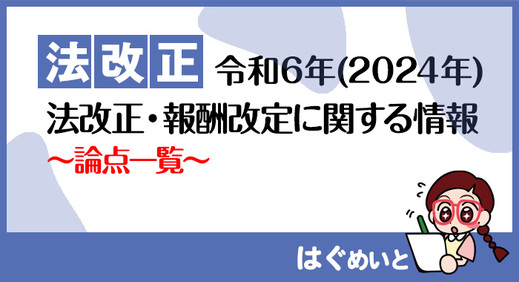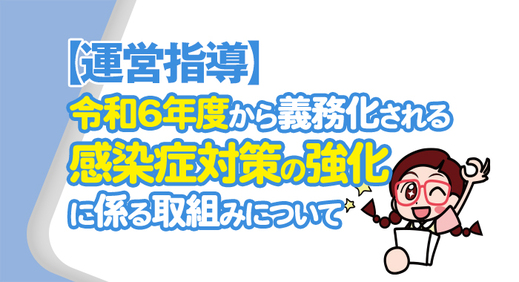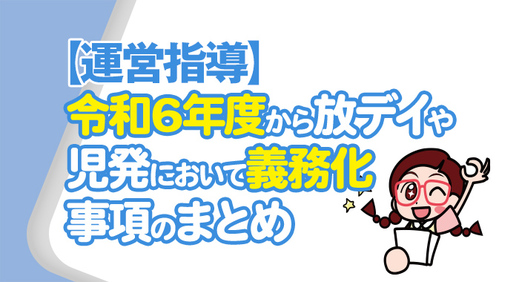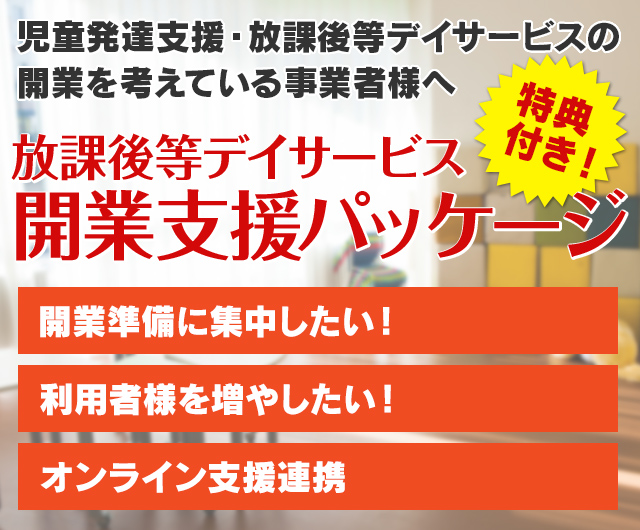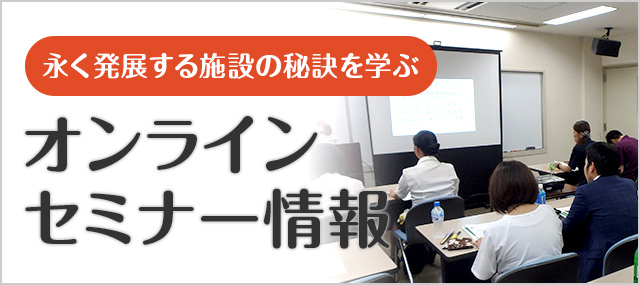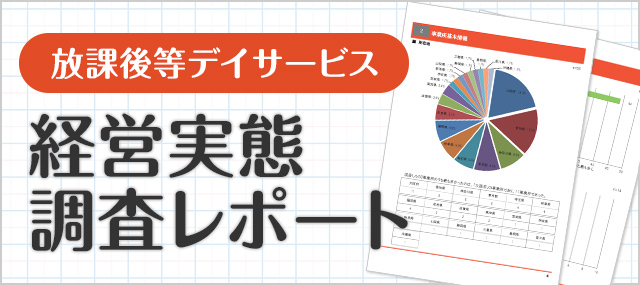放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
【加算活用事例】セルフプラン利用児童に対応する事業所間連携加算についてー令和6年報酬改定ー
2025/07/10
放課後等デイサービス 報酬改定2024
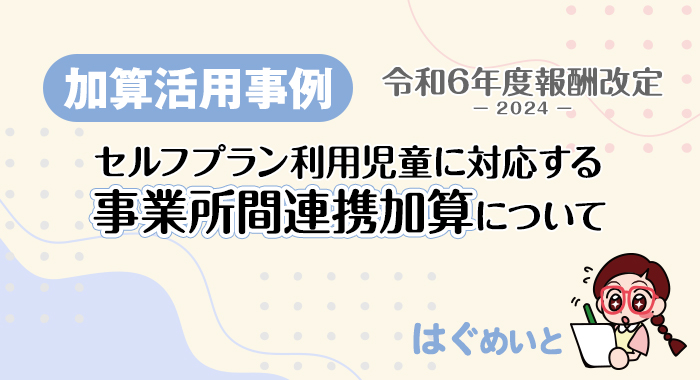
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定でセルフプランに対応するために新設された事業所間連携加算について、詳しくご紹介します。
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」令和6年4月1日
・「事業所間連携加算の創設と取扱いについて」令和6年5月2日
・「事業所間連携加算の手続等の流れ」令和6年5月2日
セルフプランとは
セルフプランを活用して障がい児通所施設を利用している児童がどのくらいいるのかご存知でしょうか?
令和4年3月の厚生労働省障害福祉課調べによると、セルフプラン率は28.9 %にのぼり、地域によってはより多くの児童が利用しています。
サービス等利用計画案は、市区町村の相談窓口で紹介された「指定特定相談支援事業者」に依頼して、児童の状態を見て保護者の希望を聞きながら相談支援専門員が作成します。
しかし、保護者自ら「サービス等利用計画案」をつくることもでき、相談支援事業所を通さずに作成した計画案を「セルフプラン」といいます。
セルフプランの課題
障がい児相談支援を利用した場合は、給付決定から更新までの間に相談支援専門員によるモニタリングが行われ、利用状況や課題等の把握・検証する機会が設けられています。
一方、セルフプランの場合は、給付決定から更新までの間に第三者によるモニタリングが行われないという課題があります。
第三者による評価が行われていないということは、子どもの課題や成長を客観的に捉える機会を失うことにつながります。
また、児童および保護者の状況等を踏まえて障がい児相談支援の利用の必要性がある場合に、適切な支援ができない恐れがあります。
事業所間連携加算とは
事業所間連携加算は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定にセルフプランに対応するために新設された新しい加算です。
事業所間連携加算
・ 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
・併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。
【事業所間連携加算(I) 500単位/回(月1回を限度)】
(1)コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合
【事業所間連携加算(II) 150単位/回(月1回を限度)】
(2) (1)の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有した場合
事業所間連携加算の取扱いについて
本加算は、障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、利用する事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定するもの
【対象となる児】セルフプランで複数事業所を併用する児
主な要件
【事業所間連携加算(I)】
※連携・取組の中心となるコア連携事業所を評価するもの
・市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた事業所(コア連携事業所)であること
・児が利用する他の事業所との間で、児に係る支援の実施状況、心身の状況、生活環境等の情報共有・支援の連携のための会議を開催すること
(※会議はオンラインの活用を可能とする。全ての事業所の参加を基本とするが、やむを得ない場合の算定も認める)
・会議の内容及び整理された児の状況や支援に関する要点について、他の事業所、市町村、保護者に共有すること
・あわせて、市町村に、児に係る各事業所の個別支援計画を共有すること。また、障害児・家族の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性
の要否を報告すること
・保護者に対して、上記の情報を踏まえた相談援助を行うこと(この場合に家庭連携加算を算定することも可能とする)
・上記の情報について、事業所の従事者に情報共有を行うとともに、必要に応じて個別支援計画を見直すこと
【事業所間連携加算(II)】
※コア連携事業所以外の事業所を評価するもの
・コア連携事業所が開催する会議に参加するとともに、個別支援計画をコア連携事業所に共有すること
(※会議の場に参加できない場合であっても、会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を行った場合には算定を可能とする)
・上記の情報について、事業所の従業者に情報共有を行うとともに、必要に応じて個別支援計画を見直すこと
※ 複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定しない。
※ 市町村は、セルフプランで複数事業所利用の場合にはコア連携事業所を定め、当該セルフプランをコア連携事業所に共有するとともに、事業所間連携加算を活用した取組を依頼することを基本とする。
また、本取組により情報共有等された児の情報を、給付決定更新の際のアセスメント等の参考とすることを基本とする(給付決定マニュアルにおいて規定)。
なお、各都道府県・市町村ごとのセルフプラン率について、今後毎年公表することを予定しており、それと併せて本加算による取組の状況についても公表することを予定
事業所間連携加算の手続きについて
手順は以下のとおりです。
● STEP1
利用予定事業所の確認
保護者からの聴き取り等により、加算対象児が利用予定である事業所を確認し、複数の児童発達支援事業所等を併用する予定があるか否かを確認すること。
(確認書に利用事業所名等を記入。)
● STEP2
保護者への説明及び同意
STEP1の結果、複数の児童発達支援事業所等を併用する予定があることが確認された場合は、加算対象児の保護者に対して、本加算の対象となる可能性がある旨及び本加算の趣旨(事業所間でセルフプランの共有や情報共有を行うことにより包括的な連携体制のもと支援を提供すること等)を説明し、保護者の意向等を踏まえながら、本加算の活用について同意を得ること。
(確認書に同意の署名を得る。)
● STEP3
コア連携事業所の候補となる事業所の選定
加算対象児の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所の候補となる事業所を選定すること。
当該事業所の選定に当たっては、本加算の要件として、保護者に対する相談援助の実施が定められていることから、当該事業所と保護者との間に信頼関係が構築されていることが重要である。
選定に当たっては、保護者の意向や加算対象児の利用状況等に応じて、以下を参考にされたい。
・ 中核機能強化(事業所)加算を算定している事業所(以下「中核拠点」という。)の利用に加えて、他の児童発達支援事業所等を利用する場合には、中核拠点をコア連携事業所として位置付けることが考えられる。
・ 上限額管理加算を算定している場合には、上限額管理事業所が中心となり、日常的に連絡調整等を行っていることが想定されるため、円滑な連絡調整を進める観点から、当該上限額管理事業所をコア連携事業所として位置付けることが考えられる。 等
● STEP4
コア連携事業所の候補となる事業所への依頼・決定
給付決定後、コア連携事業所の候補として選定した事業所に対して、事業所間の連携を実施するよう依頼し、当該事業所の承諾を得ること。
なお、依頼方法については、市町村から当該事業所への直接の依頼を基本としつつ、保護者を介して当該事業所に依頼をすることとしても差し支えない。
(確認書にコア連携事業所の情報等を記入。)
● STEP5
セルフプラン及び事業所間連携確認書の交付
給付決定時に提出されたセルフプラン及び必要事項を記入した確認書の複写を保護者及びコア連携事業所へ交付すること。
なお、交付方法については、市町村からコア連携事業所への直接の交付(送付)を基本としつつ、保護者を介してコア連携事業所に交付をすることとしても差し支えない。
● STEP6
給付決定の更新における情報の活用
事業所間連携加算を活用することにより、市町村は、コア連携事業所から、事業所間連携会議(加算対象児の支援の連携を目的とした会議をいう。以下同じ。)等において整理された情報等について報告を受けることとなることから、これらの情報等を給付決定の更新を行う際に活用すること。
(「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和6年4月)第3の3参照)
なお、障害児及び保護者の状況等を踏まえて、障害児相談支援の利用の必要性があると考えられる場合には、市町村はコア連携事業所から、その旨についても報告を受けることとなる。
この場合、地域の障害児相談支援事業所の状況等も考慮しながら、適切に障害児相談支援につなげることが求められる。
まとめ
令和6年度の報酬改定でセルフプランに対応する加算「事業所間連携加算」が新設されました。
セルフプランで事業所を複数利用する保護者に障がい児支援の適切なコーディネートを進める観点から、保護者の同意の上でコア連携事業所が中心となり、事業所間で子どもの状態や支援状況の共有等の情報連携を実施します。
コア連携事業所は、児童及び保護者の状況を踏まえて障がい児相談支援の利用の必要性を感じた場合は市町村に報告し、適切な障がい児相談支援につなげていくことが求められています。
利用児童の中にセルフプランで利用されている場合、事業所間連携加算の対象になる場合がありますので、この記事を参照の上、保護者様へ本加算をご案内することをおすすめします。
さいごに
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2024年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
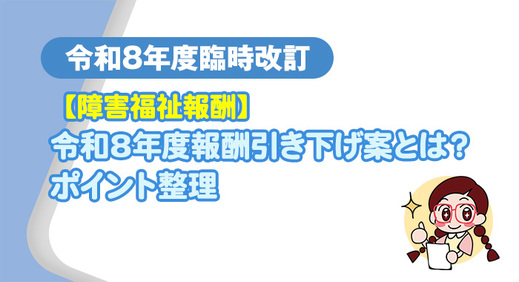
【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理
-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】
-
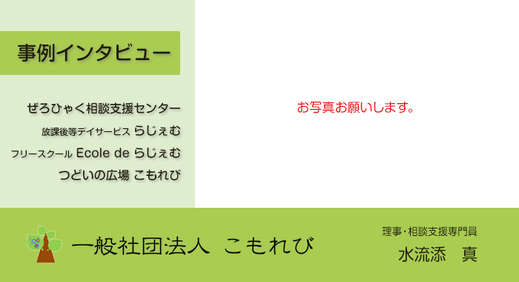
相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】
-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!
-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】
-
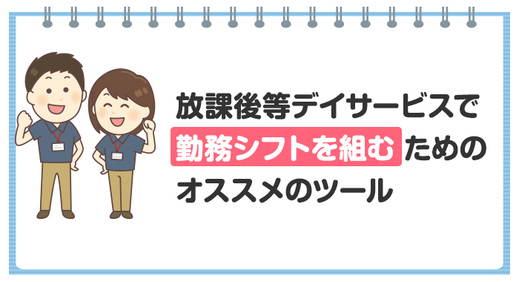
【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順
-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】
-
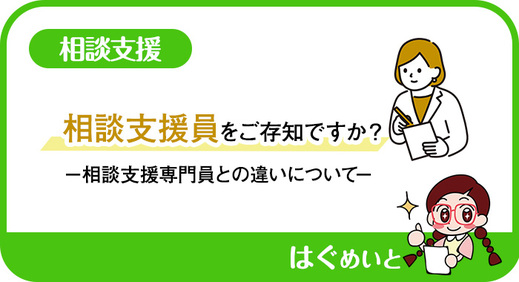
相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-
-
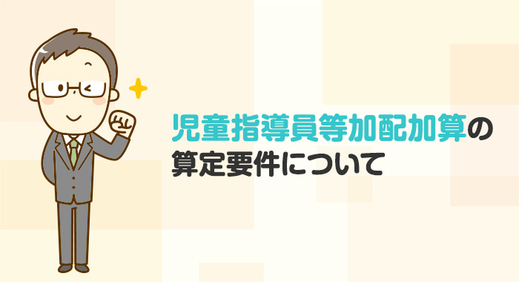
児童指導員等加配加算の算定要件について
-

「自然保育」の理念のもと保育と療育で子どもを支援【株式会社モアスマイルプロジェクト様】
-
- 話題のキーワード