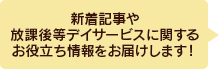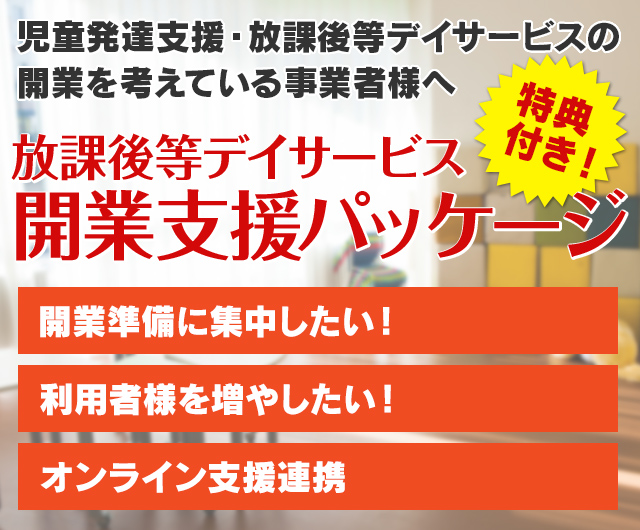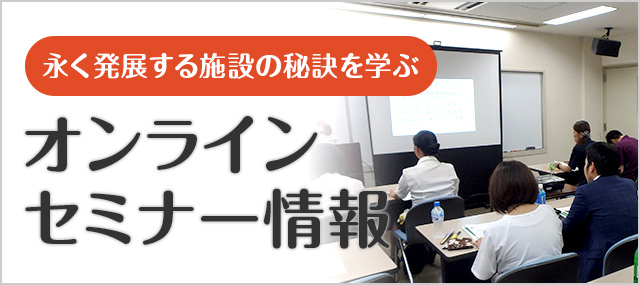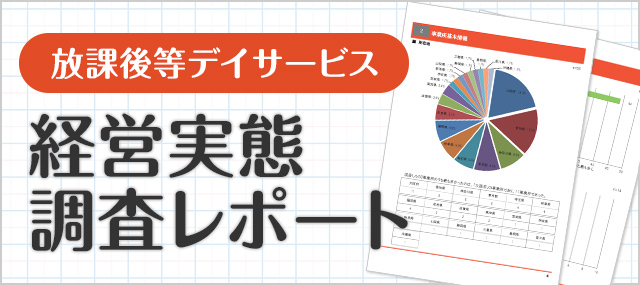放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
必要だから作った重心施設 -地域に根ざす福祉のかたち【特定非営利活動法人さくらプラス様】
2025/08/05
放課後等デイサービス事例インタビュー

三重県の名張市や桑名市で重症心身障がい児や医療的ケア児の受け入れをする重心型の児童発達支援・放課後等デイサービス「多機能型重症児デイ さくらプラス桑名星川」「多機能型重症児デイ さくらプラス桔梗が丘」を運営する特定非営利活動法人さくらプラス様にお話を伺いました。
重心施設を立ち上げた経緯などを、理事長の末永様と理事の柴田様のお二人からお話を聞くことができました。
訪問介護から障がい者支援そして重心を開所
インタビュアー(以下:イ)簡単に自己紹介をお願いします。
末永様(以下:末永)特定非営利活動法人さくらプラスの理事長の末永です。
柴田様(以下:柴田)理事をしています。柴田です。
イ)重心の施設を立ち上げられたきっかけを教えてください。
末永)今回、三重県桑名市に補助金を活用した重症心身障がい児(以下:重心児)と医療的ケア児を受け入れる「多機能型重症児デイ さくらプラス桑名星川」を開所しましたが、2019年に名張市に開所した「多機能型重症児デイ さくらプラス桔梗が丘」が初めて運営した重心施設(注1)になります。
最初、重心施設を立ち上げたのはいいけど、施設を運営するための細かなルールが分かっていなくて、県に聞いてもまだ誰も知らない頃で、厚生労働省に直接問い合わせていたほどでした。
当時は重心施設に対応したシステムがHUGしかなかったので、HUGさんにも問い合わせをさせていただきました。
イ)ありがとうございました。末永様や柴田様は、重心の関係者だったのでしょうか?
末永)全く関係ありません。私たち2人は元々は鍼灸整骨院の関係者でしたが、会社としては訪問介護からスタートしました。
当時の名張市には、居宅訪問で障がい者を支援する事業所がなかったので、訪問介護と言いながら9対1で障がい者の方がほとんどでした。それでだんだんと障がい者支援に重きを置いていく形になりました。
うちは介護スクールを運営していたこともあり、当時は人員が揃いやすい環境にありました。情報共有していた名張市からの要望もあったので重心の施設について勉強し始めました。
立ち上げてはみたものの、重心施設運営など細かいことは分からないことが多くて、名古屋の施設に見学させてもらったりしながらのスタートでした。
イ)訪問介護と送迎して施設に来てもらうのでは、随分と勝手が違ったのではないでしょうか?
末永)別物でしたね。しかし、障がい児も対応していたので訪問介護のチームの中には、いつかは施設としての居場所を用意して一般的な放課後等デイサービスをやりたいという想いもあったようでした。
しかし、「無い物は作らないといけないよね」と、まずは重心からのスタートになりました。一般の放デイを作ったのは、そのあとになります。
(注1)重心型の放課後等デイサービスは、主として重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサービス。基本的には重症心身障害児に支援を行うので、看護職員の配置が必要。利用する児童を(1)重心医ケア児、(2)重症心身障害児、(3)医療的ケア児、(4)医ケア以外(重心以外)の種別で基本報酬が異なります。
「重心の文化」という存在
イ)地域から望まれて開所されたのですね。
柴田)そうですね。厚生労働省は2023年までに各市町村に少なくとも重心の施設を1か所以上確保する目標(注2)を掲げています。
事業所を立ち上げて分かったことがあります。それは「重心の文化」という存在です。
私は広島県の福山市で事業をしていますが、重心事業所の割合も多く、46万人の人口に対して約15件ほどの事業所があります。そのため重心児についても理解があります。
重い障がいがあっても、外にどんどん出して体験をさせて、できることを増やしていく考え方が根付いています。重心事業所があるからこそ「重心の文化」が育っています。
重心事業所がない地域は、そもそも「重心の文化」が育っていないので、ご自身が利用できる制度を知らない方が多くいます。保護者の方も「うちの子も対象なのですか?」という具合です。
それは相談支援事業所においてもそうです。
重心事業所がなかった地域は、そもそも重症心身障がい児の“重症”の意味を履き違えているところにあります。“重”は重なることを意味しています。もちろん私たちも最初は分かっていませんでした。
サービス自体を理解されていないところがあるので、重心事業所は定員5名であることから説明が必要です。
また、市町村によって重心の線引きが異なり、利用できるサービスが違います。
例えば、肢体不自由の人は障害程度等級があります。知的障害の人には療育手帳(注3)があり、地域によってマルB(注3)までがサービスを利用できるなど、どこまでを重心として認めるのか、地域によって違うんです。
これから少しずつでも「重心の文化」が根付いて、地域差がなくなっていくといいですね。
(注2)第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概要
成果目標「令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。」詳しくは、こちら
(注3)療育手帳の区分について
詳しくは、こちら
研修で専門職の仕事と心得をしっかりと伝える

イ)重心施設を増やされたときに、経験が活きたことはありましたか?
末永)経験が活きるのは指定申請時ですね。あとは人集めや研修です。
重心は一般的な放デイと違い、子どもの突然の症状の悪化など、利用者の健康状態にまつわる事項が多くあります。
看護師ならともかく保育士は、冷静に受け止めて対応ができるように研修をしっかりと行う必要があります。
イ)一般でも求人には苦労しています。求人は難しいですか?
末永)専門職は苦労しますが、看護師は比較的集まりましたね。
名張で初めて看護師の求人を出したときは心配していました。夜勤がないのでどうしても病院より給料が少なくなります。それでも看護師が来てくれるのかと。
しかし、応募してくれた看護師はしっかりと定着してくれて離職率がとても低いので、一度質問したことがあります。
返ってきた答えは「看護師としては患者さんに寄り添いたいけど、病院ではそれができないから」と。
重心は定員5人で、がっつり寄り添い、子どもの成長や改善が見られるので、重心をやり始めた人たちは魅力に感じるようです。
最初はハードルがあるようですが、一般の放デイよりも定員も少ないので1人1人でじっくりと見られます。
イ)専門職員には認知度が低いので重心に集まりにくいのではないでしょうか?
末永)少ないですね。ですから学校にアプローチしています。理学療法士が放課後等デイサービスに就職できることを伝えています。
「医療」と「療育」の違いをはっきりさせる
イ)専門職員が仕事をする場合に気をつけなければならないことは何ですか?
末永)一般の放デイもそうですが、重心は特にチームビジネスです。役割分担的なことはありますが、チームで目標を達成しなければなりません。目標とは「療育」です。
一番気を付けなければならないのは、看護師が医療を持ち込みすぎないことです。
医療で話されると保育士などは委縮してしまうし、何も言えなくなってしまいます。これを最初に指導しています。「ここは、療育の場所」だと。
看護師としてお願いする部分は、「療育なんだけど、何かあったときに専門家としての知識で対応してください。」とお願いしています。
PT(理学療法士)も同じです。理学療法士を募集しているのではなくて、機能回復訓練担当職員を募集しています。「理学療法士の知識や技術を持って、機能回復訓練という職務をお願いします。」と。
分かりやすく説明すると、痙攣を起こす子に対して、
医療は、痙攣を起こさないようにすることが仕事。
療育は、成長を促すことが目的なので、いろいろな体験を用意しています。
そうすると痙攣も起こりうるので、そのときにすぐに対処していただくために看護師として勤務していただきますが、普段の仕事は療育になります。
痙攣を起こさないように大事にして過ごすのが病院になるので、そこが医療と療育の違いになります。
ここをはっきりさせておかないと、後でミスマッチが起こります。
イ)なるほど。考え方によって仕事内容も違ってくるのですね。
柴田)研修では、「医療と医療的ケア」の違いを説いて、仕事内容は医療ではなくて子育てだと伝えています。
子どもたちは、病院の中だけでずっと生活をしていくわけではなく、家庭の中で生活をしています。その余暇時間の充実のために事業所を利用する、いわば生活の一部になります。
一般の子が塾に行くように、いろいろ体験しながら機能回復訓練をする場所なので、病院のように管理して動かさないように安静にさせる場所ではないことを伝えます。
そしてQOLを上げるような訓練をしていくことで、日常生活に必要な力を付けていく場所になります。
事業所見学をされた方の感想ですが、「誰がどの職種の人なのか分からない」とおっしゃっていました。
私たちはスタッフ全員でチームとして療育をしています。ただし、看護師しかしてはいけない行為のみ、必要なときに看護師が対処します。
全員で療育をしているので、発作が起きた時など記録や見守りは保育士でもできるので、そこも全員で行います。
イ)違いを知るか知らないかで職場や仕事の印象も違ってきますね。
末永)そこを最初に教えないと、看護師も保育士も困ってしまいますし、職場に馴染めませんよね。
医療を持ち込むと「病院ではこうでした」となるので、「うちは病院ではない」と説いていきます。
柴田)医療的ケアでは、なるべくお母さんの希望に沿ったケアをしています。
毎日お世話をしているお母さんはとても詳しくて、「吸痰はこの角度から何cm入れると、この子は楽なんです」など一番分かっています。
病院では看護師が交代するので、お母さんの希望を聞き入れてくれないことも出てくるそうです。うちでは、そこの希望も汲み取って医療的ケアをしています。
イ)保護者の方の安心感もかなり違ってきますね。
支援学校との連携は不可欠
イ)名張の施設は、どのようにして認知されていったのでしょうか?
末永)支援学校によく行くので、比較的近くに開所しました。
重心クラスの子が1人でもうちに通ってくれると、日頃の活動が宣伝になっていきます。
今は重心クラスのほぼ全員がうちに通ってくれています。
イ)支援学校とはどのような関わりがあるのでしょうか?
末永)まずは送迎がありますので、どこに車を停めればいいのかなど最初から関わります。
また、ケア内容の引き継ぎもあります。重心の子は個別の手順書があるので、それを合わせていくことが必ず必要になり、毎日やり取りがあります。
イ)桑名市の施設には何人通われていますか?
末永)契約は16人ほどですが、稼働率としては90%ほどです。名張市は定員を6人に増やしても毎日ほぼ100%の状態です。
HUGはできていないことを教えてくれる

イ)HUGについてお伺いします。お役に立っている機能はありますか?
末永)HUGはまず、教えてくれることです。できていないことに対して知らせてくれるので現場では非常に役に立っています。
現場で聞いたのですが、使い方によるのか重心の名張では、送迎のときに特に役に立っていると言っていました。一般の放デイでは、保護者とのやり取りで連絡帳の機能がすごく役に立っていると言っていました。
重心は、送迎時に保護者と直接会って引継ぎもしているので、システムの連絡帳へわざわざ申し送りすることが少なくなるからだと思います。一般の放デイは、人数も多いので連絡帳機能が欠かせないものになります。
イ)教えてくれるとは、どの部分ですか?
柴田)請求業務ですね。あとは受給者証の日付やモニタリングの予定などアラートが出るのは頼もしいです。
末永)私たちもまだ運営指導(実地指導)で悩むところがあるくらいなのですが、医療的ケアに対して基本報酬でとるのか、医療連携で加算するのか、それによってルールが違ってきます。
柴田)重心事業所で医療的ケア児に対し医療連携体制加算を取得する場合は、加配が必要ない。
医療的ケアの基本報酬にプラスして看護職員加配加算IIを取得していると、最も多くなる日は6人ほどの看護師が必要になることがあります。
このあたりの報酬改定と医療的ケアのルールブックの解釈が異なる場合があります。
HUGの特許でもある人員配置も、より一層細かいケースに対応できると確認がスムーズになるので助かります。
イ)承知いたしました。社内で検討させていただきます。
HUGは直感的に操作できる
イ)HUGのいいところはどんなところでしょうか?
末永)レスポンスを含めてHUGは使いやすいです。あの使いやすさは、なんなんでしょうね。
柴田)直感的に使えるんです。今まで使ったことのないところでも、使い方が分からないけど、とりあえずやってみてもほとんど操作できてしまう。それがHUGのいいところだと思います。
あとは保護者とのやり取りで写真を添付できるところです。親はもちろん楽しみにしていますが、祖父母にシェアする人もいるようで、写真が好評なんです。
児童発達支援管理責任者が休みだったときに言われたのですが、「今日は写真UPされないのですか?」と聞かれるくらいです。見る人は、そのくらい楽しみにしてくれています。
しかし、HUGは生活介護に対応していないので、今はいいけど大人になって見ることができなくなるのは寂しいですよね。今後も使い続けていけるように生活介護も作っていただきたいです。
そのときは成長の記録として、保護者の方も放課後等デイサービスの記録を見ながら生活介護の記録をみられるようにして繋がって欲しいですね。
うちは児発・放デイ(重心)と生活介護の多機能型(注4)です。HUGは生活介護に対応していないので、HUGの他に別のソフトを使うことがとても大変なんです。これが全てHUGでできたらどれだけ有り難いことかと思っています。
完全に生活介護用でなくてもいいので、重心と生活介護がセットの重心に特化した多機能型として生活介護に対応して欲しいです。
(注4)多機能型とは、障がい福祉に関する2つ以上の異なるサービスを同じ敷地で提供する事業所です。多機能型事業所として運営できるサービス:就労継続支A型、就労継続支援B型、就労移行支援、生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
介護福祉事業に参入した先輩としてできることを

イ)重心開業のご相談を受けることがあるとお聞きしました。
末永)鍼灸整骨院の業界自体は飽和状態です。鍼灸整骨院の仲間で将来的な不安を抱えている経営者は多く、その中で私たちは介護・福祉事業をもう一つの事業の柱にしました。
鍼灸整骨院のコミュニティーがあります。その中の勉強会やセミナーで介護・福祉とはどんなものなのかといった内容について講師として呼ばれます。
鍼灸整骨院の経営者さんはホスピタリティがとても高いので、この業界に向いていると、私は勝手に思っているので、聞かれたことにどんどん答えているだけです。
柴田)指定申請はローカルルールがあり、重心特例と多機能特例の読み解き方の違いで、自治体での対応に違いが出てくることが問題です。
書いていない解釈の違いを自治体に確認することが必要で、事業所を立ち上げること自体がすごく大変なんです。
全く知らない業界の人ではないので困っていることも同じです。鍼灸整骨院業界の人が介護福祉事業に参入して、躓くことがないように、何かアドバイスできることがあればという思いからです。
「親なきあと」の地域課題に向けて
イ)最後に今後のビジョンについてお聞かせください。
柴田)親なきあとの問題は、今後出てくると思います。それは私たちの課題ではなく地域の課題です。
しかし、誰がやるのかとなると、この地域でうちしかないとなったら、やるしかないでしょうね。それを念頭に日々活動しています。
今、制度として整っているのは生活介護だけです。
重心で次に必要になるサービスは医療型の短期入所です。
医療型の短期入所施設の開所できる人の要件をご存知ですか?
有床の病院なので、私が開所しようと思ったら病院の買収もしくは一緒にやってくれるドクター探しからスタートしないといけないし、そもそもドクターを雇用する必要があります。
今、医療型の短期入所施設はどこも満員です。身内が急にいなくなり、預かって欲しいと依頼が来たときに「3か月後になります」では困るので、空きも作っておく必要があるけど空きは売上にならないので経営としては矛盾したシステムになります。
医療型の一歩前の施設で、福祉強化型の短期入所施設であれば医療的ケア児に対応できるのと、それと同時に次の住処として日中サービス支援型のグループホームを併設するなら、どうにか対応できるのではないのかと検討しています。
新しいサービスを模索しながら、公の場でもいろいろな提案ができるような活動をするしかないと思っています。
末永)だから私たちは活動を続けています。
イ)本当に勉強になります。大変貴重なお話しをありがとうございました。
さいごに
弊社が提供している「HUG」は放課後等デイサービス運営会社が開発したソフトウェアです。
請求業務はもちろん、個別支援計画やサービス提供記録の作成から管理も簡単に行えます。
実際にHUGをご利用いただいている放課後等デイサービス事業者様の感想をご紹介していますので、請求ソフトや管理システムの導入を検討されている方はご参考くださいませ。
HUG導入のお客様の声はこちら
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-

【ココトモワークス西尾】農福連携で”働く”と”居場所”の新拠点を開所
-
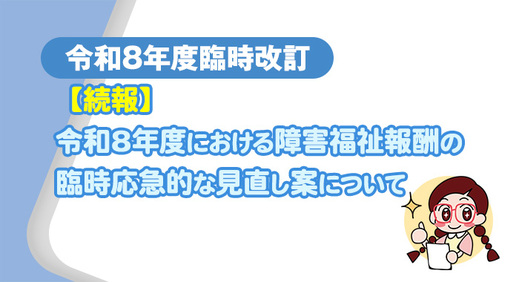
【続報】令和8年度における障害福祉報酬の臨時応急的な見直し案について
-

HUGがCareTEX東京’26に出展【就労移行・就労継続支援B型向けHUG】を先行公開!
-
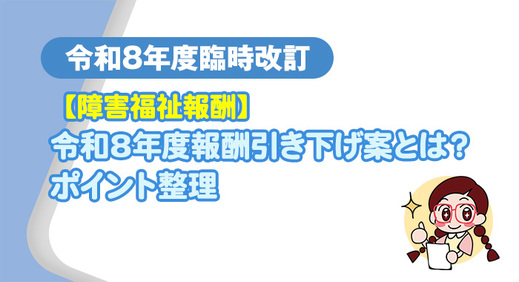
【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理
-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】
-
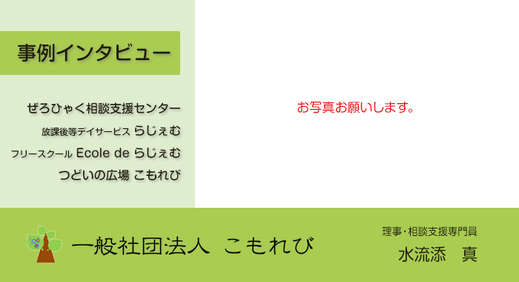
相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】
-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!
-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】
-
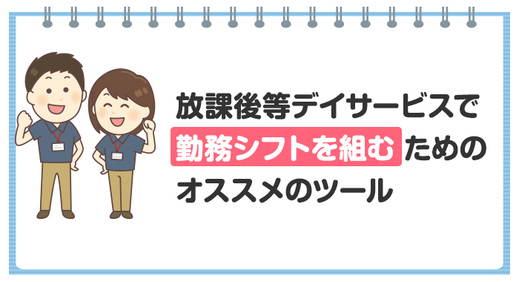
【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順
-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】
-
- 話題のキーワード